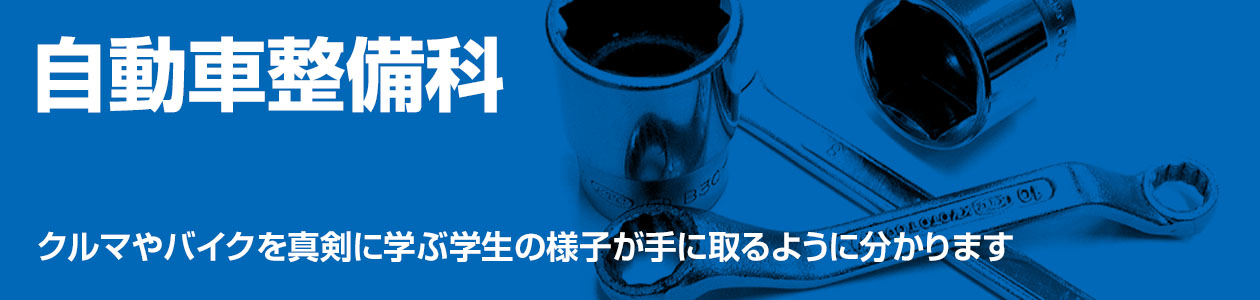皆さんこんにちは。
1年生のシャシ実習で、前回はロードスターを使用したクラッチの オーバーホール作業の様子をお伝えしましたが、今回はテラノを 使用したブレーキ編の様子をお伝えします。

このテラノたちからフロントブレーキキャリパ、リヤのドラムブレーキを 分解し構造確認とオーバーホール作業の方法、作業習熟のための分解・組立練習を行います。



以前、Vitzで同様の作業を行いましたが、車種が異なると構造や手順が異なり学生たちも苦労しながらの作業が続きます。



実習の途中には作業習熟度の確認として、設定した時間内に正確で迅速な作業が出来るかどうかの検定試験が待っています。学生の皆さん全員が一発で合格できるように一生懸命練習に励んでくださいね。
授業が終了したはずの実習場から学生の声が・・・。
覗いてみるとそこには軽自動車を整備する学生と先生の姿が・・・。 今週末に開催される1年生の軽ダート走行会に向けた車両製作、車両整備を行っていました。



ヘッドライトを取り付けたり、ブレーキのオーバーホールを行ったり、各クラスとも走行会で良い成績を修められるよう一生懸命です。
こちらは完成した車両ですか?

いずれにしても本番の大会は10月です。学生の皆さん、本番を前に車を壊さないように丁寧に走ってくださいね。
皆さんこんにちは。
先日は体育祭の様子をお伝えしましたが、今回は自動車を使った運動会ならぬ、NATS軽ダートCUP 2年プレ走行会の様子をお伝えします。この会の目的として10月に行われる全校での本大会に向けてのドライバーのローテーション、燃費計算、周回ラップタイムなどのデータ収集がメインとなっています。
2年生が手塩にかけてメンテナンスしたマシンたちです。

4月に行われた模擬走行会では、走行時間は45分でしたが今回は本大会と同じ90分間で行われます。開会式では、各種ルールの説明注意事項などが主催者のモータースポーツ科から行われその後競技開始となります。




スタート前の準備が整いセーフティーカー先導によるローリングスタートで走行開始です。




4月の走行会ではコースアウト、車両トラブルなど色々ありましたが、今回は大きなトラブルもなく順調な走行が続きます。

ドライバー交代も速やかに、タイヤ交換も手早く行っていました。さすがに2年生です。




時間は刻々と経過し90分間の走行時間が終了。全車無事にチェッカーフラッグを受けました。

90分間ダートコースを走りきると車も疲れます。


今回は2年G研クラスが優勝の栄誉に輝きました。

G研クラスの皆さん先生、おめでとうございます。
本番は1ヶ月後です。今回取れたデータを分析して本大会でも良い成績を残せるよう頑張ってください。90分間走りきったドライバーの皆さんそして各クラスの愛車たち、お疲れさまでした。
皆さんこんにちは。
前日の雨で開催が危ぶまれましたが、天気も持ち直し恒例のNATS体育祭が9月12日に盛大に開催されました。今回はその中から整備科学生の健闘ぶりをお伝えします。
競技種目NATSならではの、根性レース、タイヤ転がしリレーを含む全8種目で争われました。
ミニサッカー優勝1年G研クラス

根性レース優勝1年G研クラス

筋肉王 ベンチプレス105kgを上げた1年G研クラス 喜久川君

ソフトボール優勝2年EFクラス

教室対抗リレー優勝1年G研クラス

ご覧のように全8種目中5種目で整備科のクラスが優勝。この結果から全種目の合計得点で争われる総合成績は・・・。
見事8種目中4種目を制した1年G研クラスが総合優勝に輝きました。

担任の先生の嬉しそうな表情が印象的ですね。
学生の皆さん。十分に体のケアを行いこれからの授業に備えてください。お疲れ様でした。
皆さんこんにちは。その1に引き続きまして、クラッチオーバーホール編 その2です。
前回スタータモータが外れるところまでお伝えしましたが、その後作業が進みトランスミッションが外れる直前まで来ました。

ここから先の作業指示が出されます。


このように作業箇所をスクリーンに映し、説明が行われます。写真で分からない場合にはこのような現物で説明します。

これなら見やすいですよね。そしていよいよトランスミッションの取り外しです。



無事にトランスミッションを車両から取り外すことが出来、学生たちも嬉しそうです。


車はこのようにな状態です。この後クラッチを取り外し各部点検を行い車に取り付けます。

クラッチの取り外しは以上で終わりですが、車を元の状態に戻す作業が残っています。組み立て、取り付けを失敗すると車が走行不可能になってしまいます。1年生の皆さん最後までしっかりと作業をしてくださいね。